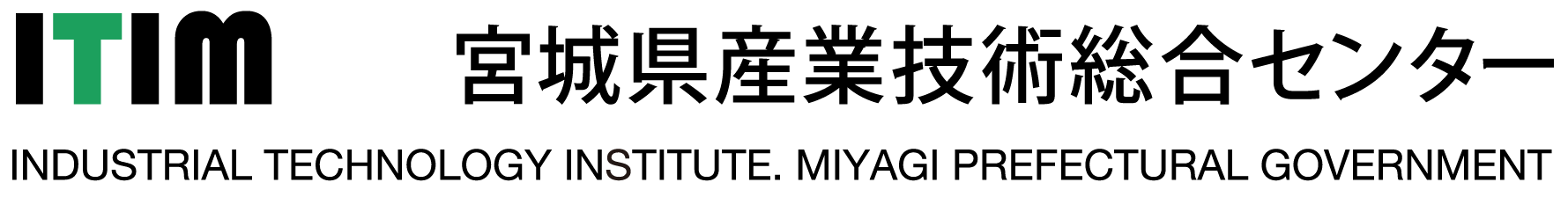2025年10月15日、株式会社ワイヤードビーンズ 代表取締役 三輪 寛氏を講師に迎え、技術の価値を最大限に引き出すためのセミナー「技術を「宝物」に変える経営 ~変化の時代に必要なマーケットイン思考~」が開催されました。
「良いものを作れば売れる時代は、もう終わりました。」セミナーの冒頭、講師の三輪寛氏はそう切り出しました。
今回、仙台を拠点に、IT事業とものづくり事業を融合させる経営で知られる株式会社ワイヤードビーンズの代表を務める同氏から、技術を単なる機能ではなく「価値」に変える視点を語ってもらいました。

「良いもの」だけでは売れない時代
三輪氏はまず、現代の市場で求められるのは「共感される価値」であると解説してくれました。製品が選ばれるためには、「信頼感、共感、ストーリー、歴史、価格」が揃う必要があり、高い技術力に加え、“誰と組み、どう売るか”という戦略の重要性が強調されました。品質が高くても、それが伝わらなければ意味がなく、製品の背景にある物語こそが顧客の心を動かすとのことです。
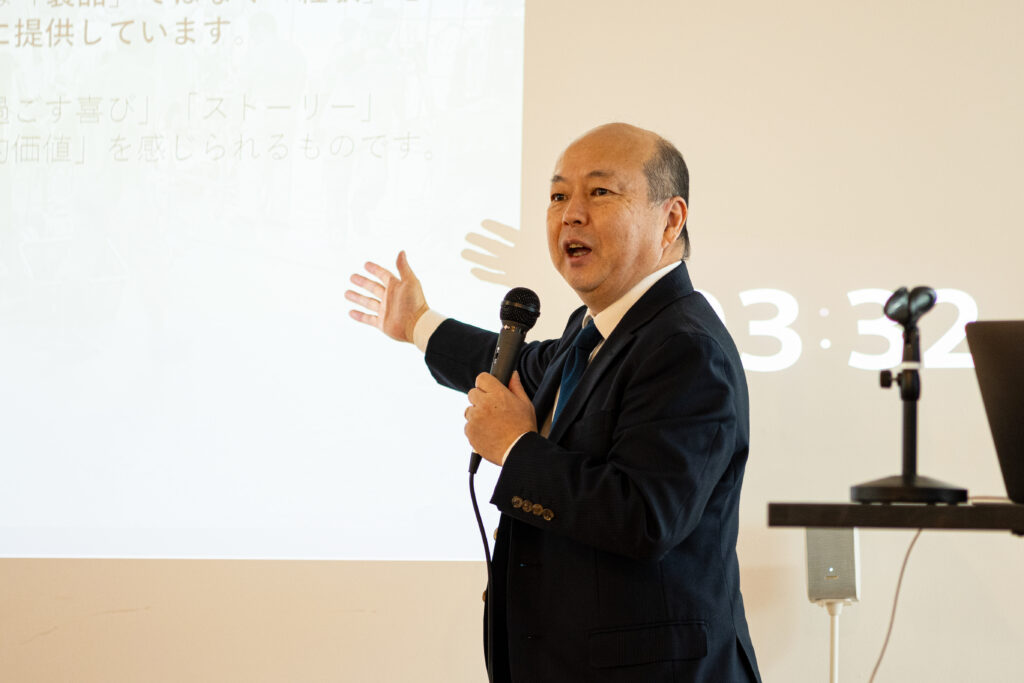
4Cで考える「経験価値」の時代
続いて三輪氏が紹介したのは「4C」の視点です。これは、従来の4P(Product・Price・Place・Promotion)を顧客視点に置き換えた考え方です。
- Product(製品)→ Customer Value(顧客価値) 顧客にとっての真の価値
- Price(価格)→ Cost(顧客が支払うコスト) 顧客側の負担(金銭以外も含む)
- Place(流通)→ Convenience(顧客の利便性) 顧客が容易に手に入れられるか
- Promotion(販促)→ Communication(顧客とのつながり) 一方的な宣伝ではなく対話
ここでは「顧客の“経験”そのものが価値になる」と三輪氏は述べています。便利さやつながりが感じられない体験は、品質が良くても心に残らないため、企業として顧客との接点をどう保つかが重要であるとのことです。


マーケットと組織のイノベーションが生む新たな市場
経済協力開発機構(OECD)が策定したオスロマニュアルには、イノベーションは「プロダクト」「プロセス」「マーケット」「組織」の4種類しかないと明記されており、三輪氏が重視するのは「マーケットのイノベーション」と「組織のイノベーション」であり、技術を“宝物”に変えるには、市場を開拓する視点が欠かせないと解説してくれました。
事例として紹介してくれた同社の代表商品「添い遂げるグラス」は、「いいものを長く使いたい」という顧客の想いに応えるため、前例の少ない「生涯保証」のサービスを導入しました。これは単なる製品保証を超えた“経験価値”の提案であり、共感を呼びブランドの信頼を築いたと話してくれました。
また、BtoB領域における工業部品メーカーの事例も紹介して頂きました。それは、外回りを担当していた社内でただ二人だけの営業担当者をあえてコールセンターに配置し、顧客情報をCRMで一元管理することで、即応性と利便性を高め、顧客との関係を深化させたという取り組みです。技術が頭打ちの市場でも、顧客との接点を再構築することで成果を上げた好事例です。


熱気に包まれた質疑応答
質疑時間では、会場の参加者から「顧客とのつながりをどう生むか」「CRMの選定基準」など実践的な質問が相次ぎ、予定を30分超えても熱気が冷めない様子でした。参加者の多くが、理論だけでなく実例に裏づけられた話に引き込まれている様子で、とても印象的でした。

まとめ
今回のセミナーで印象に残ったのは、「技術を磨くこと」と「市場で響かせること」は別次元の努力だということです。良いものを作るだけでは不完全で、そこに“人の経験”という価値をどう加えるかが重要であると学びました。そして、それを実践している三輪氏とワイヤードビーンズの取り組みが、参加された多くの企業にとって新たな視点や学びのきっかけとなったなら幸いです。
今後も、宮城県産業技術総合センターでは、これからも仕事に役立つ研修を幅広くご用意しています。開催情報は、WEBサイトやメールマガジン「ITIMオンライン」などでチェックしてみてください。
関連情報
※秘密保持のため一部画像を加工しています。